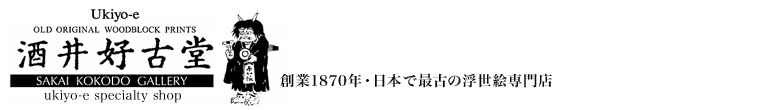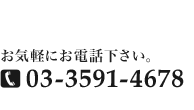浮世絵学 写楽の伝言展 しゃらく 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/115326
2025-07-19(土)写楽の伝言展 反省、提案、新見解など
[1790s南畝/本文[1941]20-2]
[1941大曲駒村/浮世繪類考20-2]
寫 樂
是また哥舞伎役者の似顔を寫せしが、あまりに眞を畫んとてあらぬさまにかきなせしかば、長く世に行はれず。一兩年にして止む。
三馬按、寫樂號東洲齋、江戸八丁堀ニ住ス。僅ニ半年餘行ハルゝノミ。
[1941駒村頭註]○冩樂。俗稱は十郎兵衛。寛政頃の人。
[1997雁註]写楽は谷素外(1734-1824)。重政、政演、政美、豊國の俳諧の師。
———————————————————————————————————————————
1844月岑/増補浮世絵類考46-3[1891]
[1891岸上操/温知叢書4-46-3]
○冩樂(住居江戸八町堀)俗稱□□ 號東洲齋
[頭注]新類考に俗稱齋藤十郎兵衛とあり。
歌舞妓役者の似顔を冩せしに、あまりに眞を畫んとて、あらぬさまに書なせしかば、長く世に行はれず。一兩年にして止む(類考)
三馬云、僅に半年餘行はるゝのみ 五代目白猿 幸四郎(後宗十郎と改)半四郎 菊之丞(富十郎)廣治 助五郎 鬼治 仲藏の類を半身に畫きたるを出せり。
——————————————————————————————————————————
1844月岑/浮世絵類考・自筆本2-08b
[1844齋藤月岑/増補浮世繪類考2-08b]
[1964板坂+棚町/近世文芸・資料と考証3/26c]
○冩樂 天明 寛政年中ノ人
俗稱 齋藤十郎兵衛 居江戸八丁堀ニ住す 阿波侯の能役者也
号 東洲齋
哥舞妓役者の似顔を写せしが あまりに真を画んとて あらぬさまに 書なせしかハ 長く世に行れず 一両年にして止む[類考]
三馬云 僅に半年餘 行るゝのミ
五代目白猿 幸四郎[后京十郎と改]半四郎 菊之丞 冨十郎 廣治 助五郎 鬼治 仲藏の類を半身に画 廻りに雲母を摺たるもの多し。
———————————————————————————————————————————
1987(1999)
西野春雄+羽田昶(ひさし)/新訂増補・能・狂言事典、平凡社
*総索引に「能役者」という術語は無い。能楽師はある。つまり、能役者は漢語で、役者(絵)を能(よ)くする意であり、写楽は全く能楽(古くは猿楽、申楽)・謡と関係がない。(2025-07-08酒井雁高・識)
写楽(-1794-1795-)は貴人であったという説が、以前からある。(森清太郎)
寛政6.05-寛政6.01 閏月があるので、10ヶ月。
・これまでにない人物の喜怒哀楽の瞬間の美、見得(みえ)を切った表情を眼、眉、口、腕、指などで最大限に表現している。
・しかも、通常の絵師は板元に遠慮するが、写楽は蔦屋の[商標]上に落款を載せている。これは、やはり只者(ただもの)ではない。
*本図は、世界で一枚だけ確認されている。(日本浮世絵博物館)
写楽の役者絵の系譜
上方(かみがた)出身であれば、当然、下記の諸画譜を見て、学んでいたに違いない。
読み下しは、まだ。
A *1780(安永9)耳鳥齋(1751-1803)/繪本水や空(みずやそら) *にちょうさい 大坂の芝居通、戯画
*浮世絵学04/外題(水や空)デジタル *影印で全頁掲載 1780耳鳥齋/水也空 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/28549
B 1782(天明2)翠釜亭(1750s-1780-)/翠釜亭戯画譜 *半身図が多い。流光齋も影響を受けていた。
*浮世絵学04/外題(翠釜亭戯画譜)すいふてい 1782(天明2)翠釜亭(1750s-1790s -)/翠釜亭戯画譜 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/80646
C 1783(天明3)流光齋(1750s -1784-1805-)/旦生言語備(やくしゃ ものいはひ) *如圭
*浮世絵学04/外題(旦生言語備 上下) 1783(天明3)流光齋[如圭]/やくしゃものいはひ 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/80364
上方出身ならば、これらを見て、学び、咀嚼する体験があって、後に写楽が出現した。写楽は、その集大成と考えると解り易い。旦は女形、生は男役。これはシナ演劇の術語。つまり、流光齋は、シナ人である。シナの宋元明清、肖像画の詳細について、私は残念ながら知らない。どなたか御存知の方がいれば、ご教示願いたい。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
〇写楽(しゃらく)/総目録_158項目
1965吉田暎二*/浮世絵事典02-047(写楽総目録)141項目 *てるじ
写楽作品の刊年、外題、板元、内題を特定したのは歌舞伎の専門家、吉田暎二*氏である。
番号は図版と一致している。図版は、かなり小さいが、図柄を特定できる。
全158 (141版画、8版下、9草稿)
役者絵の場合、「役名(役者)」が刻記されている場合は外題を特定できることがある。
しかし、殆どの作品は、役名(役者)が全く書かれていない。写楽、複製(アダチ版)第一集、41点
写楽(-1794-1795-)は貴人であったという説が、以前からある。(森清太郎)
寛政6.05-寛政6.01 閏月があるので、10ヶ月。
・これまでにない人物の喜怒哀楽の瞬間の美、見得(*みへ)を切った表情を眼、眉、口、腕、指などで最大限に表現している。
*1776(安永5)/濱松歌國(1776-1827) *上方の劇作家・浮世絵師
・しかも、通常の絵師は板元に遠慮するが、写楽は蔦屋の[商標]上に落款を載せている。これは、やはり只者(ただもの)ではない。
—————————————————————————————————————————————
写楽、これはキャラクター、蔦屋重三郎が仕組んだか(田中昭・説)。
従って、落款も微妙に違っている(大胡真人・説)
1975、オークションで新発見された写楽/二鬼を木槌で退治する図。これは偽筆(大胡真人・説)
言われてみると、二鬼に空間構図に破綻がある。木槌も造形的に不自然(田中昭・説)
—————————————————————————————————————————————
Julius KURTH(1870-1949) 牧師、蒐集家、シナ、日本版画に精通した美術史学者
ベルリン・ジム・ツム・グラウエン・クロスターに通う 学長の息子
1896 ハイデルベルグ大学で、芸術学部博士号
1897-1898 エルサレム、コンスタンティノープル、イタリア、ギリシャへの旅行
1910-1935 ベルリン・ホーエンシェーンハウゼンのタボル教会
1907UTAMARO 1910HARUNOBU 1910SHARAKU
メニュー
- F1 トップページ ukiyo-e_BEST and oldest gallery_wp-admin_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町)
- F2 御案内 ukiyo-e BEST and oldest gallery _wp-admin_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町)
- F3 通信販売 ukiyo-e_BEST and oldest gallery_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678 (東京・有楽町)
- F4 通信販売法に基づく表示 ukiyo-e BEST and oldest gallery_expression_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678 (東京・有楽町)
- F5 お問い合わせ ukiyo-e_Best and oldest gallery_contact_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)営業時間 10.00-18.00
固定ページ
- F1 トップページ ukiyo-e_BEST and oldest gallery_wp-admin_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町)
- F2 御案内 ukiyo-e BEST and oldest gallery _wp-admin_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町)
- F3 通信販売 ukiyo-e_BEST and oldest gallery_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678 (東京・有楽町)
- F4 通信販売法に基づく表示 ukiyo-e BEST and oldest gallery_expression_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678 (東京・有楽町)
- F5 お問い合わせ ukiyo-e_Best and oldest gallery_contact_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)営業時間 10.00-18.00
アーカイブ
最近の投稿
- ****浮世絵学04/略画早指南(はやおしえ)1812(文化9)北齋/略画早指南 初編 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92084 2025-12-09
- ****2025浮世絵学05/板元(はんもと)版元 屋号、略称、[商標]など 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81037 2025-12-09
- ****2025浮世絵学/歌舞音曲 1959-1966伊原敏郎(1870-1941)/歌舞伎年表 外題 役名 7200項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/9523 2025-12-09
- ****2025浮世絵学01/2025-11-10落款(らっかん)画号(雅号)索引 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1833 2025-12-09
- ****2025浮世絵学06/内題(ないだい) 外題の名数により、内題の枚数も決まってくる 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81040 2025-12-09
- *****2025浮世絵学00a/投稿一覧_1504項目(2025) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/wp-admin/post.php?post=113626&action=edit 2025-12-09
- ****2025浮世絵学00b/入力公法[7項目]1 落款 2 刊年 3 判型形態 4 外題 5 版元 6 内題 7 出典 2025-08-09 ukiyo-e(woodblock prints) Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/78569 2025-12-09
- ****2025浮世絵学00Ga/御案内_浮世絵・酒井好古堂 sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)Your PURCHASES Support the oldest ukiyo-e gallery, 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)Japanese Traditional Woodblock Prints https://www.ukiyo-e.co.jp/56558 2025-12-09
- ****2025浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)2024狂歌師(狂名)、狂歌書/総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/10336 2025-12-09
- ****2025浮世絵学00_廻る/御案内_1982日本浮世絵博物館/日本浮世絵学会 japan-ukiyoe-museum.com catalogs 酒井雁高(浮世絵・酒井好堂主人)phone 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/3879 2025-12-09
- ****2025浮世絵学04/外題(名数) (numbers of names) めいすう 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/2815 2025-12-09
- ****2025浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)浮世絵類考_その他、伝記 9968項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/498 2025-12-09
- ****2025浮世絵学02/刊年* (極改印一覧)(検索)(名主印、入力)(極印+干支年月+行事+名主)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/280 2025-12-09
- ****2025浮世絵学00_廻る/御案内_(English & Japanese) ukiyo-e BEST_and oldest gallery SAKAI Kohkodou Gallery (In front of the Imperial Tower) Japanese Traditional Woodblock Prints ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/233 2025-12-09
- ***浮世絵学01/落款(偽筆たいと)2025-11-11前北齋戴斗/(美人、雪、和傘を洋傘としてカッパ(轆轤)を下に提げている、これでは雨水が頭ロクロに入り、痛んで壊れてしまう) 東西ニューアート 偽筆 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/1171196 2025-12-08
- **浮世絵学01/落款(しゃらく)_写楽、実ハ俳人・谷素外(1734-1823)。Standard Size しゃらく大首 役者画の最高峰 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/99241 2025-12-08
- ***2025浮世絵学01Ra/落款(しゃらく)_冩樂(1734-1823*) *「能役者」、漢文で「役者(絵)を能(よ)くする(画を描く)」意で、全く謡と関係がない。この生没年は俳人・素外。Standard Size 写楽 役者絵(見得の表情)、浮世絵の最高峰 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78687 2025-12-08
- **2025浮世絵学Raa01/複製・復刻 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/114868 2025-12-08
- **2025浮世絵学Rky/ukiyo-e_oldest gallery 複製24_落款(くによし)/1842c(天保13頃)/短冊 Tanzaku, narrow Size 花鳥(魚介)鮎、緋鯉… 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/77453 2025-12-08
- ****2025浮世絵学00c/浮世絵の職人、工房(版下絵師、筆耕、彫師、摺師)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81835 2025-12-08
- 浮世絵学/歌舞音曲 2008-2012渥美清太郎(1892-1959)/系統別歌舞伎戯曲解題 五十音順 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1597 2025-12-08
- ***2025浮世絵学00/外題(奈良絵巻・奈良絵本) 2025奈良絵巻 竹とり たけとり(竹取の翁)かぐや姫 国宝級の超豪華・超詳細絵巻 2025-11-14現在 Ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3864 2025-12-08
- 浮世絵学04/略画早指南 三編 1815(文化12)北齋/画道獨稽古 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92172 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rb/落款(うたまろ)_ukiyo-e Best and oldest gallery 複製03b/うたまろ Standard Size 紅キララ_哥麿、歌麿_1795.05(寛政6.05)歌撰恋之部(紅キララ) ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78659 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Ra00/複製・復刻 ukiyo-e (woodblock prints)Best and oldest gallery: All 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)The BEST JAPAN souvenirs and memories, Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) https://www.ukiyo-e.co.jp/88211 2025-12-08
- 浮世絵学04/略画早指南 後編 1814(文化11)北齋/略画早指南 後編 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92136 2025-12-08
- ****2025浮世絵学07/出典(しゅってん) 西暦(和暦)著者/書名 これが基本 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81040 2025-12-08
- ***2025浮世絵学04/外題(文化藝術懇話会47b)竹取物語 竹とり(かぐや姫、羽衣伝説)について 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/35765 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rh/ukiyo-e_複製14/廣重 Standard Size ひろしげ_廣重/名所江戸百景 色々 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/51925 2025-12-08
- ***2025浮世絵学04/和本、版本、活字本_御案内 デジタル phone 03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) https://www.ukiyo-e.co.jp/51460 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Ra/ukiyo-e oldest gallery 複製01/復刻 うたまろ他 Standard Size 手摺木版 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)The BEST Japanese Traditional Woodblock Prints, Handmade reproduction (adm. by JUM) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/41940 2025-12-08
- ***2025浮世絵学01Raa/ukiyo-e(woodblock prints)_Best and oldest gallery 御案内 浮世絵は、海外の御土産に最適 Ukiyo-e (pictures of the people, by the people and for the people)Best Japan Souvenirs and memories 浮世絵学・全般 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/39072 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rb/ukiyo-e_BEST and oldest gallery 複製08/美人(哥麿)Standard size 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/34253 2025-12-08
- ****浮世絵学/歌舞音曲 1956-1966伊原敏郎(1870-1941)/歌舞伎年表 2015酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/9540 2025-12-08
- ****2025浮世絵学03/判型形態_(1)和紙 (2)和紙 浮世絵 版本 (3)奉書 版型形態 寸法 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/4654 2025-12-08
- ****浮世絵学/歌舞音曲 2025-11-30K-FINAL A 外題五十音 B 役名(役者) C 編年・西暦 D その他 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3145 2025-12-08
- ***2025浮世絵学01/落款_廻る/1941小島烏水*(1873-1948)_ukiyo-e(woodblock prints)_BEST and oldest gallery *うすい/浮世絵類考(序文)9968項目 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)落款、五十音 Biography of ukiyo-e artists 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1783 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rcs/ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製23/カラーシート Standard Size 浮世絵の三枚続、お風呂、文明開化絵を縮小 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/100 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rhi/落款(ほくさゐ ゐいつ)複製04/北齋爲一_Thumbnail (小さな)爲一/冨嶽三十六景 爲一(ゐいつ)期の世界で尤も有名な作品 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/33 2025-12-08
- **2025浮世絵学V1a/ミニ動画6-12_ 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/115012 2025-12-04
- **浮世絵学01/酒井庄吉(1878-1942) 1925亀清樓 Gookin(1853-1936) ほか 1925酒井庄吉ほか、亀清樓、兩國 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92285 2025-12-04
- **2025浮世絵学R00/複製・復刻(順序摺り)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/114856 2025-12-04
- **2025浮世絵学01/1790大田南畝(1749-1823) 「類」の絵師/浮世絵類考(うきよえるいこう)正編ほか 「類」の絵師ほか 146項目 他429項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/82344 2025-12-04
- **2025浮世絵学R_08-24 複製・復刻 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/116455 2025-12-04
- **2025浮世絵学Ra00/複製・復刻 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/114867 2025-12-04
- ***浮世絵学04/(支那學・文化藝術懇話会)支那學・研究一覧(邪馬台国、帰結)三國志(魏志)と隋書 古田武彦 九州王朝* 帰結、ずばり九州(阿蘇山と書かれている)(古田武彦/九州王朝*)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/37595 2025-12-04
- 浮世絵学 懇話会133 2025-12-19(金)18.00-20.00 峰崎博次/松平定信 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/117579 2025-12-04
- *2025浮世絵学04/外題(げだい) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81034 2025-12-04
- ***浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)らっかん_「ひらがな」で入力 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81027 2025-12-04
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)2025-12-04狂歌師/総目録 らっかん 編年 生没 狂歌師 狂歌書 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/89352 2025-12-04
- **2025浮世絵学04/1799(寛政11)蕙齋(けいさい)/人物畧画式 外題(人物畧画式)(人物略画式)デジタル *影印で全頁掲載 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)http://www,ukiyo-e.co.jp/28069 2025-12-04
- **2025浮世絵学01/落款(◯◯◯◯) 浮世絵師、狂歌師、戯作者など伝記集成 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/104011 2025-12-04
- **浮世絵学04/外題(長崎絵)2028-07-05長崎絵(ながさきえ)/総目録 884項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp9957 2025-12-04
- *2025浮世絵学V1a_ミニ動画_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/116294 2025-12-04
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯)2025-10-05U-FINAL総目録 218,131項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/97236 2025-12-04
- ***浮世絵学/歌舞音曲 1926飯塚/歌舞伎細見_役名 五十音順ほか 2015-06-24現在 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1608 2025-12-04
- **1967酒井泉三郎・北齋漫画 殷の妲己、証明書、台北・国立歴史博物館 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/117511 2025-12-04
- **2025浮世絵学01/落款(えし)かみがたえ なにわ 上方絵 模式図(編年)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/80961 2025-12-04
- *2025浮世絵学 V1a/ミニ動画_7-12_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/115167 2025-12-04
- *2025浮世絵学03cR _reproduction_複製03/うたまろ_哥麿、歌麿/歌撰戀之部 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78622 2025-12-04
- *2025浮世絵学V1b_ミニ動画_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/92533 2025-12-04
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)_らっかん 2025-08-09総目録_連番+らっかん 218,029項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/115624 2025-12-04
- **浮世絵学01/落款(◯◯◯)_浪花絵師 なにわえし なにわゑし 上方絵 大阪 京 名古屋 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/ 83431 2025-12-04
- 2025浮世絵学R05a _reproduction_複製05a/廣重 ひろしげ/名所江戸百景 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) 電話 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/77061 2025-12-04
- 2025K浮世絵学(縄文時代の土偶)2021竹倉史人(1976- )たけくら ふみと 酒井雁高 https://www.ukiyo-e.co.jp/78395 2025-12-04
- **浮世絵学04/外題(長崎絵) 1938内田六郎/長崎版画目録 紅日書樓藏 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/9908 2025-12-04
- **2025浮世絵学01/落款(◯◯◯◯) ひらがな 浮世絵師/総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3495 2025-12-04
- *浮世絵学 V2_ミニ動画_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/114940 2025-12-04
- **2025浮世絵学0a/入力公法_ukiyo-e(woodblock prints) 01落款 02刊年 03判型形態 04外題 05板元 06内題 07出典 08全文 ほか 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) Japanese Traditional Woodblock Prints ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) https://www.ukiyo-e.co.jp/56701 2025-12-04
- **2025浮世絵学Rb/ukiyo-e_oldest gallery 複製10/美人ほか Standard Size 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/34409 2025-12-04
- **2025浮世絵学Ru/ukiyo-e_oldest gallery 複製07/歌麿 Standard Size うたまろ_婦人相學十躰・(ぽっぴん) 順序摺 ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/13503 2025-12-04
- **2025浮世絵学00/御案内_ukiyo-e oldest gallery in Japan: 浮世絵学データベース DB編(原画また画像の文字情報を浮世絵学に沿って入力)浮世絵学*複製 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/1041/n 2025-12-04
- **2025浮世絵学Rip/いっぴつせん_ 一筆箋 (大揃、単品) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/211 2025-12-04
- ***2025浮世絵学Ru/落款(うたまろ)_哥麿、歌麿_ サムネール(小さい)_歌麿/浮世絵美人絵の最高峰 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/162 2025-12-04
- **2025浮世絵学Rt /たんざく_複製/短冊など Standard size. 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/41 2025-12-04
- ***2025浮世絵絵Rh/落款(ひろしげ)_廣重/東海道五十三次 サムネール 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/17 2025-12-04
- 浮世絵学01/貞信2(さだのぶ2)(1848-1940)総目録_125項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/99087 2025-12-01
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯)狂歌師_唐花忠紋 五律から哥 住吉浦近 うたまろ_哥麿/美人半身 三種 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) *https://www.ukiyo-e.co.jp/13696 2025-12-01
- 浮世絵学01/春重(はるしげ) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/82304 2025-12-01
- K浮世絵学04/懇話会92 2021-12-18太田光彦/私の映画(5)フランス ヌーベル・ヴァーグ 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/87122 2025-12-01
- 2025K浮世絵学04/外題(文化藝術懇話会)懇話会 すべて 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/35962 2025-12-01
- *2025浮世絵学00G/御案内_ukiyo-e(woodblock prints)_BEST_oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/88214 2025-12-01
- *2025浮世絵学03/版型形態(はんけい・けいたい) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81032 2025-12-01
- *2025浮世絵学01G/落款(ことんど)_言人(1900-1976)[酒井・川口版]御案内_ukiyo-e(woodblock prints) oldest gallery 浮世絵・酒井好古堂 sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)Your PURCHASES Support the oldest ukiyo-e gallery, 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)Japanese Traditional Woodblock Prints https://www.ukiyo-e.co.jp/107952 2025-12-01
- K浮世絵学04/懇話会96 2022-06-25(土)17.00-18.00 高尾裕子(たかお ゆうこ)/私の好きな映画(仮題) https://www.ukiyo-e.co.jp/90742 2025-12-01
- 浮世絵学01/光溪(こうけい)、役者似顔、現代の写楽 2022-09-23 8点 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92918 2025-12-01
- 2025浮世絵学/俄(にわか)らっかん順_総目録_353項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/70222 2025-12-01
- 2025浮世絵学04/1797(寛政9)蕙齋(けいさい)/鳥獣畧画式(鳥獣略画式) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) http://www,ukiyo-e.co.jp/22488 2025-12-01
- 1940Eumorfopoulos(1863-1939)/The Eumorfopoulos Collections, Sothey’s 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/113627 2025-12-01
- K浮世絵学04/懇話会93 2022-02-26峰崎博次/原節子(1920-2015) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/86284 2025-12-01
- K浮世絵学04/懇話会95 2022-05-28(土)17.00-18.00 酒井雁高/フェリーニ(1920-1993)https://www.ukiyo-e.co.jp/87089 2025-12-01
- K浮世絵学04/懇話会90 2021-11-27太田光彦/私の映画(4)フランス映画史 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/86284 2025-12-01
- 浮世絵学 2023(令和5)藝能学会(折口信夫、奥野信太郎、伊藤好英)/年刊 藝能 第29号 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/113429 2025-12-01
- 浮世絵学01落款/吟雪 、房信(ぎんせつ、ふさのぶ) 1772-1777吟雪(1740s-1777-)/竹林七賢人_酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/877858 2025-12-01
- K浮世絵学04/懇話会91 2022-01-29太田光彦/私の映画(5) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/86284 2025-12-01
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯) らっかん+判型形態… 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/102231 2025-12-01
- K浮世絵学04/懇話会94 2022-04-23西島 勉/チャップリンの世界(仮題) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/87003 2025-12-01
- *浮世絵学01/落款(えし)ひらがな五十音順 伝記集成+総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/69501 2025-12-01
- *2025浮世絵学0b/入力公法+ ukiyo-e_01落款 02刊年 03判型形態 04外題 05板元 06内題 07出典 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/53709 2025-12-01
- 浮世絵学01/貞信1(さだのぶ1)(1809- 1823-1839-1879)(さだのぶ1)/伝記集成19項目 総目録546項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/23973 2025-12-01
- *浮世絵学01/落款(うたまろ1)歌麿1 2024-06-20歌麿1(うたまろ1)/総目録_3842項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/23223 2025-12-01
- *浮世絵学01/落款(うたまろ1)哥麿1 、歌麿1 2021哥麿/総目録 3,565項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/21466 2025-12-01
- **浮世絵学01/落款(◯◯◯)狂歌師、狂歌書_DB データベース 2021狂歌師+狂歌書目 Kyouka poets & books 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/19592 2025-12-01
- 2025浮世絵学G10/御案内_メディア報道 酒井好古堂(および日本浮世絵博物館)の紹介 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/16453 2025-12-01
- *2025浮世絵学Rh/ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製12/廣重 Standard Size ひろしげ_東海道五十三次・日本橋 順序摺 ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/13483 2025-12-01
- *浮世絵学01/落款(うたまろ1)歌麿1_1978歌麿/総目録 1978浮世絵聚花03 (二代を含む)2015-06-24現在 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/2184 2025-12-01
- *2025浮世絵学00G/御案内_ukiyo-e(woodblock prints) oldest gallery sakai_kohokodo gallery (Tokyo, yurakucho) ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp /1453 2025-12-01
- *2025浮世絵学Rip/ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製10/一筆箋 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)phone 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/209 2025-12-01
最近の投稿
- ****浮世絵学04/略画早指南(はやおしえ)1812(文化9)北齋/略画早指南 初編 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92084 2025-12-09
- ****2025浮世絵学05/板元(はんもと)版元 屋号、略称、[商標]など 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81037 2025-12-09
- ****2025浮世絵学/歌舞音曲 1959-1966伊原敏郎(1870-1941)/歌舞伎年表 外題 役名 7200項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/9523 2025-12-09
- ****2025浮世絵学01/2025-11-10落款(らっかん)画号(雅号)索引 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1833 2025-12-09
- ****2025浮世絵学06/内題(ないだい) 外題の名数により、内題の枚数も決まってくる 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81040 2025-12-09
- *****2025浮世絵学00a/投稿一覧_1504項目(2025) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/wp-admin/post.php?post=113626&action=edit 2025-12-09
- ****2025浮世絵学00b/入力公法[7項目]1 落款 2 刊年 3 判型形態 4 外題 5 版元 6 内題 7 出典 2025-08-09 ukiyo-e(woodblock prints) Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/78569 2025-12-09
- ****2025浮世絵学00Ga/御案内_浮世絵・酒井好古堂 sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)Your PURCHASES Support the oldest ukiyo-e gallery, 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)Japanese Traditional Woodblock Prints https://www.ukiyo-e.co.jp/56558 2025-12-09
- ****2025浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)2024狂歌師(狂名)、狂歌書/総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/10336 2025-12-09
- ****2025浮世絵学00_廻る/御案内_1982日本浮世絵博物館/日本浮世絵学会 japan-ukiyoe-museum.com catalogs 酒井雁高(浮世絵・酒井好堂主人)phone 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/3879 2025-12-09
- ****2025浮世絵学04/外題(名数) (numbers of names) めいすう 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/2815 2025-12-09
- ****2025浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)浮世絵類考_その他、伝記 9968項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/498 2025-12-09
- ****2025浮世絵学02/刊年* (極改印一覧)(検索)(名主印、入力)(極印+干支年月+行事+名主)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/280 2025-12-09
- ****2025浮世絵学00_廻る/御案内_(English & Japanese) ukiyo-e BEST_and oldest gallery SAKAI Kohkodou Gallery (In front of the Imperial Tower) Japanese Traditional Woodblock Prints ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/233 2025-12-09
- ***浮世絵学01/落款(偽筆たいと)2025-11-11前北齋戴斗/(美人、雪、和傘を洋傘としてカッパ(轆轤)を下に提げている、これでは雨水が頭ロクロに入り、痛んで壊れてしまう) 東西ニューアート 偽筆 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/1171196 2025-12-08
- **浮世絵学01/落款(しゃらく)_写楽、実ハ俳人・谷素外(1734-1823)。Standard Size しゃらく大首 役者画の最高峰 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/99241 2025-12-08
- ***2025浮世絵学01Ra/落款(しゃらく)_冩樂(1734-1823*) *「能役者」、漢文で「役者(絵)を能(よ)くする(画を描く)」意で、全く謡と関係がない。この生没年は俳人・素外。Standard Size 写楽 役者絵(見得の表情)、浮世絵の最高峰 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78687 2025-12-08
- **2025浮世絵学Raa01/複製・復刻 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/114868 2025-12-08
- **2025浮世絵学Rky/ukiyo-e_oldest gallery 複製24_落款(くによし)/1842c(天保13頃)/短冊 Tanzaku, narrow Size 花鳥(魚介)鮎、緋鯉… 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/77453 2025-12-08
- ****2025浮世絵学00c/浮世絵の職人、工房(版下絵師、筆耕、彫師、摺師)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81835 2025-12-08
- 浮世絵学/歌舞音曲 2008-2012渥美清太郎(1892-1959)/系統別歌舞伎戯曲解題 五十音順 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1597 2025-12-08
- ***2025浮世絵学00/外題(奈良絵巻・奈良絵本) 2025奈良絵巻 竹とり たけとり(竹取の翁)かぐや姫 国宝級の超豪華・超詳細絵巻 2025-11-14現在 Ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3864 2025-12-08
- 浮世絵学04/略画早指南 三編 1815(文化12)北齋/画道獨稽古 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92172 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rb/落款(うたまろ)_ukiyo-e Best and oldest gallery 複製03b/うたまろ Standard Size 紅キララ_哥麿、歌麿_1795.05(寛政6.05)歌撰恋之部(紅キララ) ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78659 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Ra00/複製・復刻 ukiyo-e (woodblock prints)Best and oldest gallery: All 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)The BEST JAPAN souvenirs and memories, Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) https://www.ukiyo-e.co.jp/88211 2025-12-08
- 浮世絵学04/略画早指南 後編 1814(文化11)北齋/略画早指南 後編 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92136 2025-12-08
- ****2025浮世絵学07/出典(しゅってん) 西暦(和暦)著者/書名 これが基本 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81040 2025-12-08
- ***2025浮世絵学04/外題(文化藝術懇話会47b)竹取物語 竹とり(かぐや姫、羽衣伝説)について 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/35765 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rh/ukiyo-e_複製14/廣重 Standard Size ひろしげ_廣重/名所江戸百景 色々 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/51925 2025-12-08
- ***2025浮世絵学04/和本、版本、活字本_御案内 デジタル phone 03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) https://www.ukiyo-e.co.jp/51460 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Ra/ukiyo-e oldest gallery 複製01/復刻 うたまろ他 Standard Size 手摺木版 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)The BEST Japanese Traditional Woodblock Prints, Handmade reproduction (adm. by JUM) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/41940 2025-12-08
- ***2025浮世絵学01Raa/ukiyo-e(woodblock prints)_Best and oldest gallery 御案内 浮世絵は、海外の御土産に最適 Ukiyo-e (pictures of the people, by the people and for the people)Best Japan Souvenirs and memories 浮世絵学・全般 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/39072 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rb/ukiyo-e_BEST and oldest gallery 複製08/美人(哥麿)Standard size 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/34253 2025-12-08
- ****浮世絵学/歌舞音曲 1956-1966伊原敏郎(1870-1941)/歌舞伎年表 2015酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/9540 2025-12-08
- ****2025浮世絵学03/判型形態_(1)和紙 (2)和紙 浮世絵 版本 (3)奉書 版型形態 寸法 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/4654 2025-12-08
- ****浮世絵学/歌舞音曲 2025-11-30K-FINAL A 外題五十音 B 役名(役者) C 編年・西暦 D その他 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3145 2025-12-08
- ***2025浮世絵学01/落款_廻る/1941小島烏水*(1873-1948)_ukiyo-e(woodblock prints)_BEST and oldest gallery *うすい/浮世絵類考(序文)9968項目 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)落款、五十音 Biography of ukiyo-e artists 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1783 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rcs/ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製23/カラーシート Standard Size 浮世絵の三枚続、お風呂、文明開化絵を縮小 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/100 2025-12-08
- ***2025浮世絵学Rhi/落款(ほくさゐ ゐいつ)複製04/北齋爲一_Thumbnail (小さな)爲一/冨嶽三十六景 爲一(ゐいつ)期の世界で尤も有名な作品 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/33 2025-12-08
- **2025浮世絵学V1a/ミニ動画6-12_ 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/115012 2025-12-04
- **浮世絵学01/酒井庄吉(1878-1942) 1925亀清樓 Gookin(1853-1936) ほか 1925酒井庄吉ほか、亀清樓、兩國 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/92285 2025-12-04
- **2025浮世絵学R00/複製・復刻(順序摺り)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/114856 2025-12-04
- **2025浮世絵学01/1790大田南畝(1749-1823) 「類」の絵師/浮世絵類考(うきよえるいこう)正編ほか 「類」の絵師ほか 146項目 他429項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/82344 2025-12-04
- **2025浮世絵学R_08-24 複製・復刻 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/116455 2025-12-04
- **2025浮世絵学Ra00/複製・復刻 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/114867 2025-12-04
- ***浮世絵学04/(支那學・文化藝術懇話会)支那學・研究一覧(邪馬台国、帰結)三國志(魏志)と隋書 古田武彦 九州王朝* 帰結、ずばり九州(阿蘇山と書かれている)(古田武彦/九州王朝*)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/37595 2025-12-04
- 浮世絵学 懇話会133 2025-12-19(金)18.00-20.00 峰崎博次/松平定信 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/117579 2025-12-04
- *2025浮世絵学04/外題(げだい) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81034 2025-12-04
- ***浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)らっかん_「ひらがな」で入力 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81027 2025-12-04
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)2025-12-04狂歌師/総目録 らっかん 編年 生没 狂歌師 狂歌書 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/89352 2025-12-04
- **2025浮世絵学04/1799(寛政11)蕙齋(けいさい)/人物畧画式 外題(人物畧画式)(人物略画式)デジタル *影印で全頁掲載 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)http://www,ukiyo-e.co.jp/28069 2025-12-04
- **2025浮世絵学01/落款(◯◯◯◯) 浮世絵師、狂歌師、戯作者など伝記集成 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/104011 2025-12-04
- **浮世絵学04/外題(長崎絵)2028-07-05長崎絵(ながさきえ)/総目録 884項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp9957 2025-12-04
- *2025浮世絵学V1a_ミニ動画_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/116294 2025-12-04
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯)2025-10-05U-FINAL総目録 218,131項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/97236 2025-12-04
- ***浮世絵学/歌舞音曲 1926飯塚/歌舞伎細見_役名 五十音順ほか 2015-06-24現在 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1608 2025-12-04
- **1967酒井泉三郎・北齋漫画 殷の妲己、証明書、台北・国立歴史博物館 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/117511 2025-12-04
- **2025浮世絵学01/落款(えし)かみがたえ なにわ 上方絵 模式図(編年)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/80961 2025-12-04
- *2025浮世絵学 V1a/ミニ動画_7-12_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/115167 2025-12-04
- *2025浮世絵学03cR _reproduction_複製03/うたまろ_哥麿、歌麿/歌撰戀之部 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78622 2025-12-04
- *2025浮世絵学V1b_ミニ動画_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/92533 2025-12-04
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯◯)_らっかん 2025-08-09総目録_連番+らっかん 218,029項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/115624 2025-12-04
- **浮世絵学01/落款(◯◯◯)_浪花絵師 なにわえし なにわゑし 上方絵 大阪 京 名古屋 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/ 83431 2025-12-04
- 2025浮世絵学R05a _reproduction_複製05a/廣重 ひろしげ/名所江戸百景 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) 電話 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/77061 2025-12-04
- 2025K浮世絵学(縄文時代の土偶)2021竹倉史人(1976- )たけくら ふみと 酒井雁高 https://www.ukiyo-e.co.jp/78395 2025-12-04
- **浮世絵学04/外題(長崎絵) 1938内田六郎/長崎版画目録 紅日書樓藏 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/9908 2025-12-04
- **2025浮世絵学01/落款(◯◯◯◯) ひらがな 浮世絵師/総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3495 2025-12-04
- *浮世絵学 V2_ミニ動画_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/114940 2025-12-04
- **2025浮世絵学0a/入力公法_ukiyo-e(woodblock prints) 01落款 02刊年 03判型形態 04外題 05板元 06内題 07出典 08全文 ほか 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) Japanese Traditional Woodblock Prints ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) https://www.ukiyo-e.co.jp/56701 2025-12-04
- **2025浮世絵学Rb/ukiyo-e_oldest gallery 複製10/美人ほか Standard Size 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/34409 2025-12-04
- **2025浮世絵学Ru/ukiyo-e_oldest gallery 複製07/歌麿 Standard Size うたまろ_婦人相學十躰・(ぽっぴん) 順序摺 ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/13503 2025-12-04
- **2025浮世絵学00/御案内_ukiyo-e oldest gallery in Japan: 浮世絵学データベース DB編(原画また画像の文字情報を浮世絵学に沿って入力)浮世絵学*複製 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/1041/n 2025-12-04
- **2025浮世絵学Rip/いっぴつせん_ 一筆箋 (大揃、単品) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/211 2025-12-04
- ***2025浮世絵学Ru/落款(うたまろ)_哥麿、歌麿_ サムネール(小さい)_歌麿/浮世絵美人絵の最高峰 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/162 2025-12-04
- **2025浮世絵学Rt /たんざく_複製/短冊など Standard size. 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/41 2025-12-04
- ***2025浮世絵絵Rh/落款(ひろしげ)_廣重/東海道五十三次 サムネール 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/17 2025-12-04
- 浮世絵学01/貞信2(さだのぶ2)(1848-1940)総目録_125項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/99087 2025-12-01
- *浮世絵学01/落款(◯◯◯)狂歌師_唐花忠紋 五律から哥 住吉浦近 うたまろ_哥麿/美人半身 三種 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) *https://www.ukiyo-e.co.jp/13696 2025-12-01
- 浮世絵学01/春重(はるしげ) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/82304 2025-12-01
- K浮世絵学04/懇話会92 2021-12-18太田光彦/私の映画(5)フランス ヌーベル・ヴァーグ 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/87122 2025-12-01
- 2025K浮世絵学04/外題(文化藝術懇話会)懇話会 すべて 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/35962 2025-12-01
- *2025浮世絵学00G/御案内_ukiyo-e(woodblock prints)_BEST_oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/88214 2025-12-01
- *2025浮世絵学03/版型形態(はんけい・けいたい) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/81032 2025-12-01